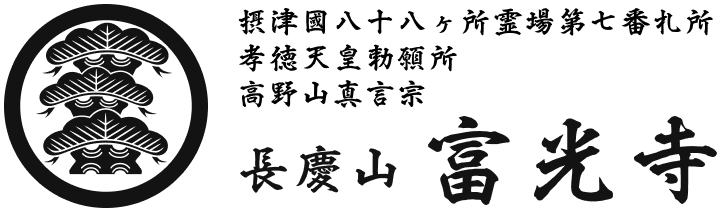法事のすすめ

法事とは
法事とは、仏法の行事という意味です。
仏事、追善(追薦、追福)、供養、年回、年忌などとも呼びます。
※追善(ついぜん)とは、亡くなった人の冥福を祈って、生きている人が善行をすること、または、その善行によって故人の霊を供養することです。
いうまでもなく、故人や先祖の命日(亡くなった日=忌日)や年回(三年目、七年目など)にあたって、お寺さんを招いて仏事を営むのですが、ひとくちに法事といっても、その規模によって、いろいろ開きがあります。
親の命日に、お寺さんにお参りしてもらい、短い読経をお願いする「月忌」法要に、盆やお彼岸のお参りといった年中行事化したものから、七回忌、十三回忌といった年回法要、五十回忌、百回忌といったかなり大がかりな法事が営まれるものでさまざまです。
法事の規模と意味
いわゆる「月まいり=月忌」にお寺さんが来るときは、家に居合わせた家族だけが読経に会うごくひっそりとしたものですし、お寺さんの接待を茶菓子程度ですが、年回法要になると親戚の人や知人にも集まってもらって、お勤めの後の会食(お斎)ということになりますし、五十回忌、百回忌には、法事というよりもむしろ「お祝い」といった雰囲気で、夜を徹しての豪華な宴になる例もあります。これは50年、100年と「家」が続き、ご先祖をおまもりしてきたということは、めでたいかぎりにほかならず、普通の法事より豪華に致します。
法事に込められたこころ
「法事」を営むこころは、こうした祖先への「おかげさまで」という思いに出発しています。亡き両親を思い、先祖のご恩をしのぶという営みは、おりにふれ行われるのがもちろん望ましいのです。
祈りの意味と私たちの生き方
これらの行為は日常生活において安心を得る大きな役割があると考えられています。つまり、良い人生を送りたいと願う私たちが、目に見えない世界を信じ、祈ることです。祈りの行為が日常に存在しているのです。この世の中を生きる上で、自分の思い通りになることばかりではありません。ほとんどが思い通りにならないことばかりです。それをわかっていながら、自分の祈りがどこかに通じ、反映されることを心の根底で願っているのです。つまりその対象が神仏であったり、先祖であったり、自らの行為であったり、さまざまなものを私たちは信じ頼り生きています。
仏教における「縁起」と善行の意味
こうした習慣には、仏教でいう「縁起」という考え方が影響を与えていると考えられます。「縁起」とはすべての物事がさまざまな原因・条件によって生じているということです。この世に存在するものすべては、永遠不変な存在ではなく、さまざまな影響を受けて変化し続けているのです。つまり悪い原因には悪い結果が、良い原因には良い結果が生まれるということです。法事、供養、祈祷などの仏事を行うことが良い原因を作ると考えます。
※参考:法事のしきたり(仏教文化研究会)、青少年のための仏教読本(高野山真言宗布教研究所)
(年)年回忌法要早見表 ※ご逝去年をご参考ください。
| 一周忌 | ||
|---|---|---|
| 三回忌 | ||
| 七回忌 | ||
| 十三回忌 | ||
| 十七回忌 | ||
| 二十三回忌 | ||
| 二十五回忌 | ||
| 二十七回忌 | ||
| 三十三回忌 | ||
| 三十七回忌 | ||
| 五十回忌 | ||
| 百回忌 |